お知らせ >> 学校図書館Q&A >> C.資料の整理や選択
|
C. 資料の整理や選択
上記以外のご質問がある方は、こちらのフォームをご利用ください。 |
|
A : 図書の分類は、小学校や中学校の学校図書館でも、NDC(日本十進分類法)にそって分類すると良いでしょう。
分類番号と配架(書架に並べること)は、請求記号(図書の背に貼ってある、主に3段のラベルに書いてある記号です。)によって、ほぼ同じ結果になることを、よく承知しておきましょう。 NDCは、その図書の内容を、端的に表現している数字を使ったコード番号です。ですから、NDCのコード構成を知っていると、図書の題名からはわからない、図書の中味もわかってきますし、書架の中に、関連する図書が結果的に集まることにもなります。 学校によっては、NDC分類を与えていても、教科で使う本をひとまとめにしたり、シリーズ本をひとまとめにして配架している所がありますが、「総合的学習の時間」での利用を中心として、「調べる学習」が進んでくると、結局は目的とされる図書が見つけられなくなってしまう。ということになってしまいます。 A : 図書の背中のラベルに書かれている数字や記号全体を、「請求記号」と呼びます。
普通、3段ラベルの場合は、 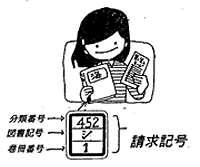
この請求記号は、書架のどのあたりに、その図書が入っているのかを知る、「図書の住所」のようなものです。カードやコンピュータの目録にも同じ記号が記入されているので、検索すると、その図書の配架場所がわかるのです。 A :
■ 書架の並び方 ■
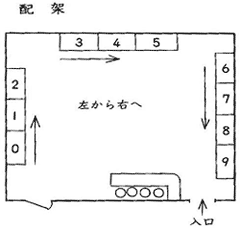 ○ 図書館の資料(主に図書)は、書架に入っています。 ○ 図書館の資料(主に図書)は、書架に入っています。その書架は、資料についている背ラベルの番号順に大きな固まりで、図書室内の左から右の方向に並んでくのが基本形です。(図書室の建物の関係で若干の違いがある場合もあります) 図書室の様々なルールが、子どもたちにとって、法則性がわかるようにしておくことが、何よりも基本となります。 ※ 参考資料 はこちら A : 背ラベルは、色別けラベルでもあります。この各色を利用して、分類ごとに色を決めたいと思うのは自然の道理りです。問題は、どの分類をどの色にするかと言うことです。
幸か不幸か、分類と色の関係についての規格のようなものはありません。 電気製品の部品の、抵抗やコンデンサなどは、JISなどの規格があるのですが。回答者自身も一時、色分けを抵抗やコンデンサのJISカラーコードと対応させようとしましたが、不発に終わっています。 さて、多くの学校で採用されている色別を参考に示します。
ついでに、背ラベルを貼る位置は、背の地から15mmにしているのが最も多いケースです。 もう一つ、学校の蔵書を示すバーコードラベルを使用している場合は、右とじ、左とじに関係なく背を左にして、表紙または裏表紙の真ん中に(バーコードラベルは左右の中央に中心が来るようにして)、地から2センチメートルの位置に貼るという仕様にしている学校が最も多いケースです。 A : ポイントは、以下の3点です。
しかし、レンタルビデオを使っての上映会となるとどうでしょうか…。 レンタルビデオは、
学校の上映会に用いるビデオソフトは、きちんと映写会をしても良い。というように著作権上の許諾が行われているソフトを使用しましょう。 |
戻る | ↑このページの先頭へ
